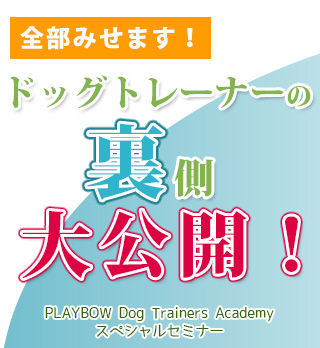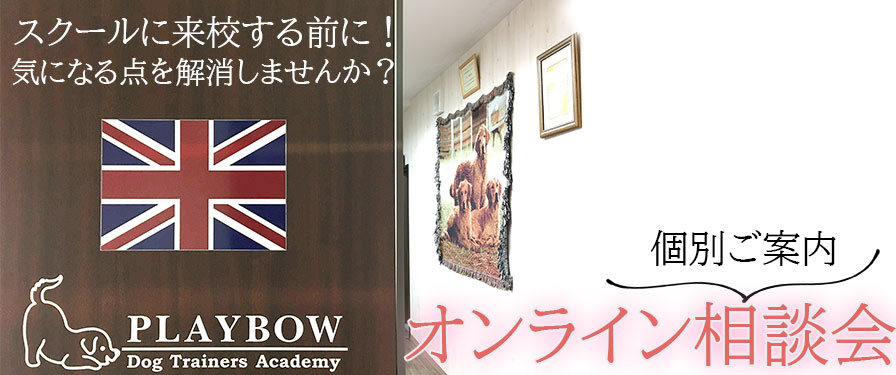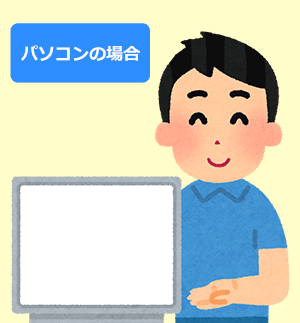ずーっと悩んでいます その2
こんにちは。プレイボゥドッグトレーナーズアカデミー事務局と講師も務めております佐藤ですU^エ^U 前回に続き、悩んでいること はい!本日は前回の続きをお届けします! 前回の内容まだ見ていないよ~という方はこちらからご覧い […]
ずーっと悩んでいます
こんにちは。プレイボゥドッグトレーナーズアカデミー事務局と講師も務めております佐藤ですU^エ^U ずっと悩んでいること 早速ですが、佐藤はずーーーーーっと悩んでいることがあります。 それは度々ブログで書かせていただいてい […]
犬に関わるなら絶対知っておくべきヒト
こんにちは。プレイボゥドッグトレーナーズアカデミー事務局と講師も務めております佐藤ですU^エ^U ドッグトレーニング業界の先駆者 前回のメールマガジンではモチベーショントレーニングの1つであるおやつの選び方をご紹介させて […]
ハザードマップを活用しよう
こんにちは。プレイボゥドッグトレーナーズアカデミー講師の矢川です。 1年半ほど前に犬の聖地(犬連れの聖地)という場所をご紹介するメルマガを書かせていただきました。 その場所は東京の世田谷区にある駒沢公園で「犬の聖地」で検 […]
外の刺激におやつが勝てない!
犬に関するセミナーが盛り沢山♪ こんにちは!プレイボゥドッグトレーナーズアカデミー事務局の瀬尾です。 先日、外部講師をお招きした生徒さん向けのセミナーが開催されました! 講師は、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、 […]
ロングリードにはご注意を!
ロングリード、使ったことありますか? こんにちは!プレイボゥドッグトレーナーズアカデミー事務局の瀬尾です。 さっそくですが、皆さまは犬にロングリードを装着して遊んだり走らせたことはありますか? 現在、生後半年のゴールデン […]
犬が排泄を外す理由は人側にも原因が
こんにちは。プレイボゥドッグトレーナーズアカデミー講師の矢川です。 突然ですが、皆さんは職場に愛犬を連れていく事は出来ますでしょうか? いわゆる<愛犬同伴出勤>は可能かどうか、という事です。 なぜ、この話題を取り上げたの […]
大型犬を10頭トレーニング?
こんにちは。プレイボゥドッグトレーナーズアカデミー講師の矢川です。 今週始めには都内でもかなりの積雪となりました。 8センチぐらいの積雪となったようですね。 月曜日の夕方から降り出して、翌日火曜日の朝に自宅の窓を開けたら […]